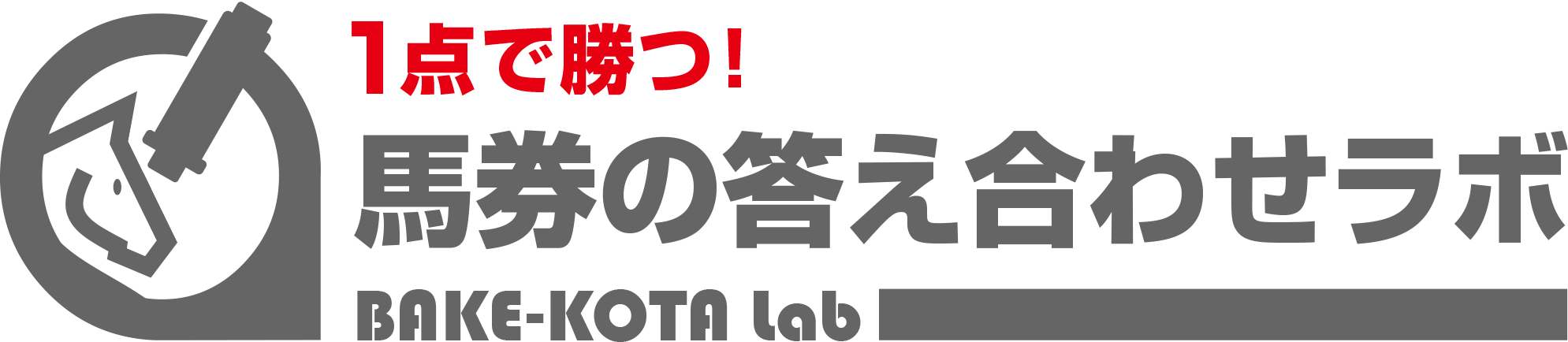先日、無敗の5連勝でプロキオンSを制覇したヤマニンウルスについて、管理調教師のある発言が競馬ファンを驚かせました。
「競馬に飽きているように見える」――。
近走のヤマニンウルスは惜しいレースを挟みながらも4連敗と連勝時の勢いに陰りを見せていました。
調教師のこの発言は、調教タイムや過去の戦績といった“数字”だけでは読み取れない、「馬の気持ち」がレースに影響を及ぼしていることを強く感じさせるものでした。
【参考:サンスポZBAT!】アンタレスS7着のヤマニンウルスは放牧へ
https://www.sanspo.com/race/article/general/20250422-QERX3DOVGRKZPBM2TCESUFJG7M
データ予想や調教タイムでは測れない「馬の気持ち」がレース結果に影響しているのならば、どのようにそれを予想に反映するべきなのか?
この記事では、「競走馬のメンタル」を切り口に、予想スタイルの幅を広げるヒントをご紹介します。
実際にあった「走らなくなった馬」たちの事例
- デビューから連勝し、大物と期待されたが尻すぼみになった馬
- あるレースをきっかけに全く走らなくなった馬
- 調教では絶好調でも、本番になるとまったく走らない馬。逆に調教では地味なのに、レースでは好走する馬
肉体的な衰えではなく、「競馬に飽きた」「やる気を失った」といった精神面が、パフォーマンスを左右している可能性があります。場合によっては「メンタルが壊れた」と評される場合もあります。
最近だと不良馬場の宝塚記念を勝った後、秋シーズンに大敗を重ねたブローザホーンや、3歳にして天皇賞・秋と有馬記念を制しながら、以降5着が最良着順だったエフフォーリアが思い起こされます。
もちろん競馬は複数頭で競うレースですので、結果には展開などメンタル以外の不確定要素が大きく関わってくるものですが、あきらかに格上の実績をもった馬が、条件を変えても何度も大きな敗戦を繰り返すのは、何か一貫した理由を疑いたくなります。
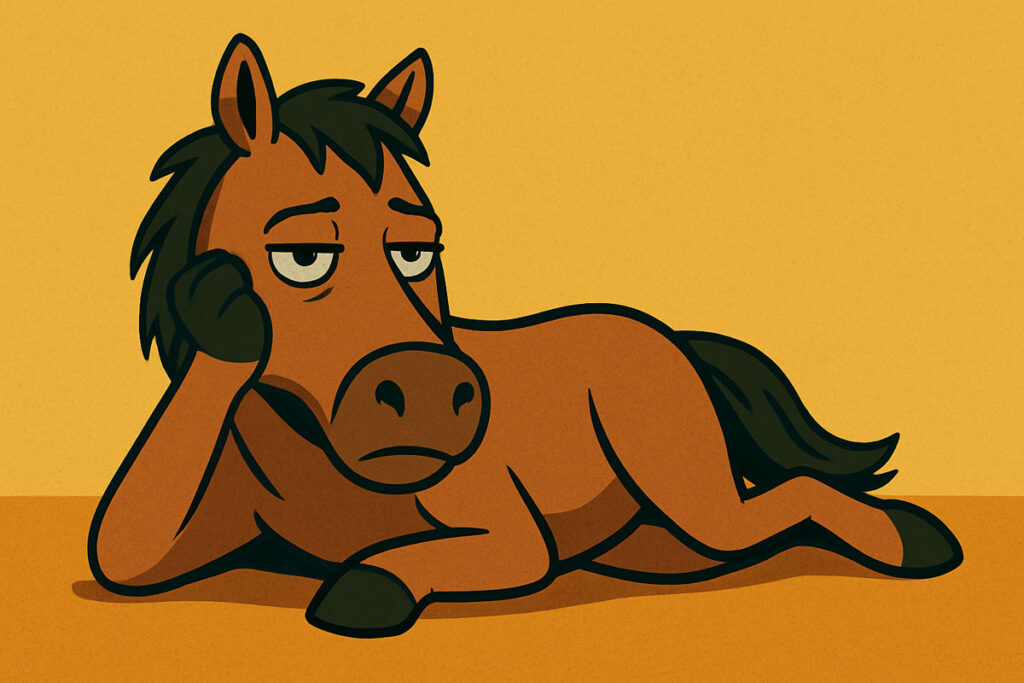
早熟の陰に潜む“気持ちのピーク”
こうした馬、特に2・3歳で活躍し、4歳以降負けを繰り返した馬は「早熟」と評されることもあります。ですが「早熟」とされる馬の中には、肉体的にはまだ成長途上であるにもかかわらず、精神的に“燃え尽きて”しまった馬もいるかもしれません。
- レース中の故障やハイペースなどの消耗戦によって「競馬=苦しいもの」という記憶が定着してしまった
- レース中に「競馬を覚えさせる」ため手綱を絞りすぎたことで、本来の前進気勢がなくなってしまった
また馬も経験を積む中で、“手を抜く”ことを覚えます。
- レースでも調教でも「全力で走らなくても叱られない」と解釈した馬
なかには古くは「五冠馬」シンザンのように調教は全く動かないのに、レースでは完勝する馬もいます。ですがどの競走馬も多かれ少なかれレースを理解し、慣れていくことで、レースで全力を出さなくなっていきます。いわゆる「ズブくなる」状態で、騎手のゴーサインへの反応が鈍くなっていくようです。
他の馬より「少し早く」上記のいずれかの状態になった馬は、レースで本気を出さず・出せず、結果的に「早熟」とされてしまうことがあるように思います。
ちなみに競走馬の競争寿命自体は延びているケースが増えてきている
2023年に11歳セン馬のマイネルプロンプトが“JRA最高齢平地勝利記録”を樹立し、同年のGⅠ高松宮記念では8歳馬のトゥラベスーラが3着になりました。ほかにも2015年のかしわ記念を9歳で制したワンダーアキュート、特殊な例では19歳で没するまで「生涯現役」だった地方馬ヒカルアヤノヒメ(なんと16歳で馬券内3着の実績あり)など、高齢ながら活躍する馬が21世紀以降増加傾向にあります。
これは調教技術の進化がもたらしたものという面が強いですが、身体的調教の進化だけではなく、メンタル面における調教の進化の影響も大きいといわれています。
昔は調教をすればするだけ走るというスパルタ的な考えがありましたが、今は身体のこと、そしてメンタル的なところも重視するようになったことが、競争寿命の長寿化に繋がっていると思います。
『一般社団法人 福島馬主協会 コラム「馬の体」 消耗度と競争寿命』 より
上記コラムの中で獣医師の方もこのように語っています。
馬の気持ちをどう予想に反映すればいいのか?
さて少し話が脱線しましたが、では「馬の気分」はどうやって予想に活かせば良いのでしょうか?
パドックや調教からこうしたメンタルを測るのは困難なように感じます。プロである調教師や厩務員自体も試行錯誤しているのですから、我々一般人は同じ視点からのアプローチで勝算はないように思えるのです。
そこで紹介したいのが今井雅宏氏の「Mの法則」の考え方です。
20世紀末に登場した、サラブレッドの心身状態を分析した理論。サラブレッドは競馬という閉じられたシステムで走っている為(中央競馬の場合なら、更にその中のJRAというシステム)、人間以上に強いストレスを抱えて走っている。そのストレスが強いと凡走するというのが基本概念。
今井雅宏『Mの法則(競馬理論) 用語集』 より

弟子の亀谷敬正氏ともども「馬は走る距離を知らない」ということもよく言われていますが、距離短縮・延長のローテーションや血統がもつ性格特性をもとにレースを予想する手法です。
例えば、Sタイプに分類される馬は闘争心が強く、一本調子に走ろうとする性質があります。 このタイプは気性をコントロールするために、短縮などのショック療法が有効とされています。 また、馬の状態がフレッシュであることを「鮮度」と呼び、休み明けや条件替わり、メンバー替わり、格上げ戦、位置取りショックなどで鮮度は上がるとされています。
今井雅宏氏は書籍を何冊も刊行されていますし、ウェブ上で予想の販売もしていますので、興味をもった方はぜひその考え方に触れてみてください。今井氏に私淑している予想家(もしくは知らず知らずのうちにその影響下にある予想家)は多いことからも、この予想理論の根幹である「馬のメンタル」が重要な予想ファクターであることを多くの人が認めている証左なのかもしれません。
生き物が走る競技だからこそ、馬の気持ちを考えることは重要
競馬の予想といえば、過去の成績や調教タイム、ラップ分析などの“数値”が中心になりがちです。
するとついつい馬という生き物ではなく、数字や機械のような無生物が走っているような錯覚に陥ります。
しかし、先述のヤマニンウルスの事例に見られるように、競走馬は感情を持つ生き物。ときにやる気を失い、競馬に飽き、走る気をなくすこともあるのです。
そんな「馬の気分」を観察し、想像し、データと併せて読み解くことは、確実に新しい予想の武器になります。
特に、他人と同じ買い方に埋もれてしまいがちな今だからこそ、“見えない要素”に目を向けることで、あなただけの「勝ちパターン」が見つかるかもしれません。
数字だけに縛られず、時に“馬の心”を読む――それも競馬の奥深さであり、予想の醍醐味ではないでしょうか。